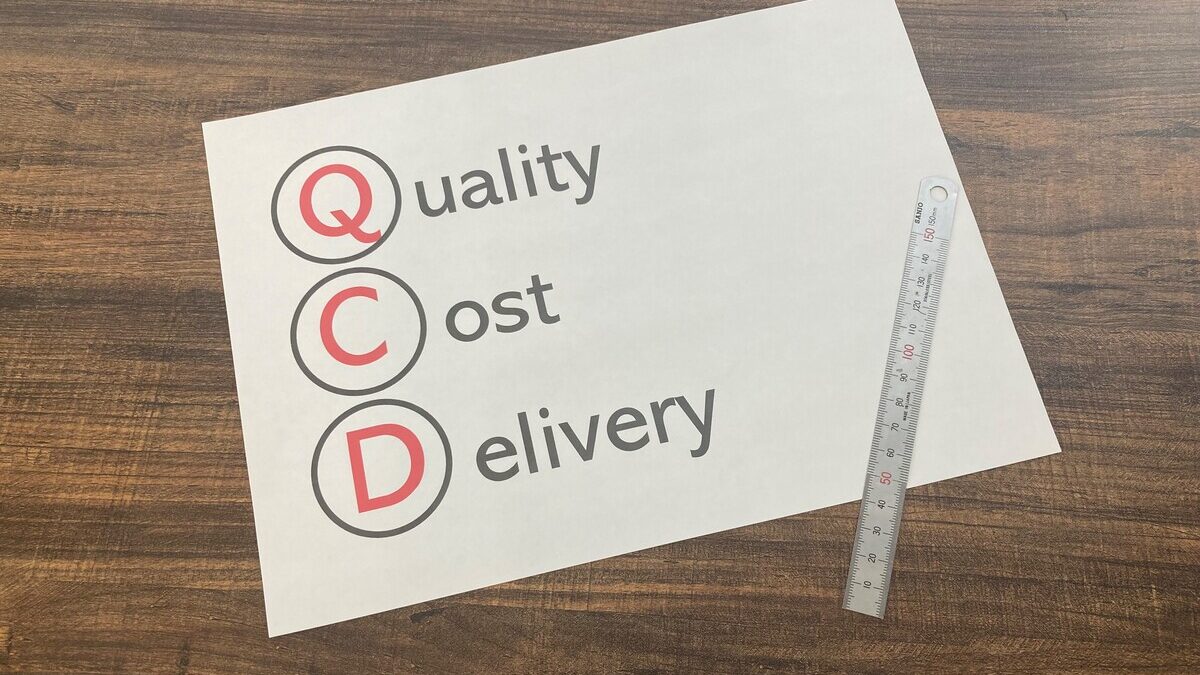QCDとは
- quality
- cost
- delivery
の頭文字を抜き出したものです。
QCDで現状を把握し、強みを伸ばし、弱みを克服していく事で、当社のセールスポイントになってくるはずです!
QCDと呼ぶ意味
製造業にとっての付加価値を切り分けると、品質(quality)・コスト(cost)・納期(delivery)となり、この3つが強みの源泉となっています。
お客様から評価されているのはQCDのどれなのかを考えると当社の強みを見つけやすいです。
強みの裏返しは弱みとなりますので、弱みも品質・コスト・納期になって表れます。
自分達の強み・弱みを把握するうえで、品質・コスト・納期に注目してみると、より詳細を把握できるようになります。
重要なのは3つ合わせて考えることです。
なぜならば中小企業では生産資源が限られますのでQCDはトレードオフの関係が色濃く現れるからです。
- 品質を高めれば、コストがかかりやすい。
- 納期を早めれば、品質が高めにくい。
- コストを下げれば、品質が落ちやすい。
品質・コスト・納期とは
品質・コスト・納期についてあらためてみてみたいと思います。
特に強みの源泉となる付加価値として考えてみましょう。
QCDの品質とは
品質はお客様が求めるものである事が最も重要です。
お客様が求めていないような機能・精度を付けても評価にはつながりません。
ただし、社内基準もムダではありません。
お客様が当社を「他社よりも品質が良い」と認識してくれるように、品質基準を見直していきましょう。
一言で品質といっても、色々な要素があります。
図面通り作る事は当然の事ながら、お客様が感じる品質は、下記のような点でも評価されます。
- 性能・機能など基本的要件で評価
- 見た目・肌触り・香り・色・味など、人間の感覚で評価
- 実際に使用した時の効率性・耐久性・安全性などで評価
- バリや切粉がないかなどで評価
- 他
私は食品工場向けの機械部品を作っていたので、バリや切粉については絶対クレームになるため、最も注意する事の一つでした。
逆に精度はあまり気にせず、先方の指定した公差について確認すると、「大きければいい」といったおおざっぱな返答が返ってきました。実際に精度でクレームがつく事はほぼありませんでした。
このようにお客様にとって「一番重要な事」と、作業者が思う「重要な事」に差が出る事がありますので、改めてお客様の業界についても考えてみると良いでしょう。
QCDのコストとは
コストはお客様の価値観に左右されます。
他社との相見積もりによる比較がありますが、発注決定要素としては、価格だけではありません。
- 品質が良い方を選ぶ会社
- 納期が早い(遅れがない)方を選ぶ会社
といった自社にとってメリットの大きい会社を選ぶことになるでしょう。
さらに価格が少し高い場合にも、お客様によって判断が異なるでしょう。
- 迷わず安い方を選ぶ会社
- 少しだけ高いだけなら品質を重視する会社
- 少しだけ高いだけなら納期を重視する会社
といったQCDのどれを重要視するかで判断が分かれる事になります。
さらに相見積をせずに注文をくれるような会社もあります。
そういった場合の比較基準はどうなっているのかを知る必要があります。
- 過去の価格と比較する会社
- 自社独自で算出した価格と比較する会社
- 信頼しており、比較をあまりしない会社
など同じ相見積もりをしないにしても、状況は大きく違うでしょう。
自社独自で算出した価格を持つ会社は価格にはかなりシビアで、少しでも合わなければその旨を伝えてくるか、他社に出してしまいます。
一方比較をあまりしない会社は価格よりも品質や納期面であなたの会社を信頼している事でしょう。
このように相手の業界・状況・お付き合いの長さ・社風など色々な要素でお客様の判断基準に違いがあります。
お客様を知る事で、柔軟な価格決定をしていく事も可能となります。
QCDの納期とは
納期もお客様の業界・状況・社風などで評価に違いが出てきます。
担当者の感覚の違いも大きく出てくるのが特徴です。
- 予定通りに入っていれば問題ない
- とにかく早く納品してもらって安心したい
- とりあえずの注文でも〇日以内としておこう。
このように人によって、納期についてのバラツキが出てきます。
相手と良くコミュニケーションをとって、本当に必要な日を教えてもらえるようになるだけで、生産の平準化が可能となるはずです。
納期の管理の価値が高まってきている。
短納期の価値が以前よりも上がってきています。
製品のライフサイクルが短くなってきていますので、早く作って早く売る事が求められています。
そのため、お客様のスケジュールが過密となり、取引先に求めるものも短納期を優先する事が増えてきているのです。
私の支援した短納期特化型のサービスを開始した会社はそれだけで新規取引先がかなり増えましたし、大手からの注文も入るようになりました。
品質やコストについてはこれまでも頑張って強化してきたはずですので、短納期に対応できる力も伸ばして、それをウリにする事で新たな価値を生み出す事が出来ると考えます。
重要なのは新たな価値である事を大事にする事。
お客様の指定する納期よりも早く収める事は新たな価値を下げてしまいます。
お客様が求めれば、価格を上げて対応するのが理想でしょう。
最近は恩に感じてくれることも少ないので、特急価格を+αでもらいたいものです。
QCDSとは

QCDSはQCDにService=サービスを加えたものです。
付加価値について、製造業では品質・コスト・納期で表してきたわけですが、サービス業や小売店などで付加価値を把握するうえで、サービスが追加される事があります。
モノからコトへと変化をしてきた現在では、製造業においても例外ではなく、QCD以外にお客様が喜んでくれる、便利になるような「サービス」についても把握すべきでしょう。
- 御用聞き=訪問時に必要なものを確認して受注してくる。担当者が楽。
- 自社配達=時間の指定や特急時など、時間単位での対応で担当者が助かる。
- 梱包=お客様の指定するボックスに入れて納品や、キチンと梱包するなどお客様のその後の使い道に合わせて対応するので担当者が楽。
- 製図=お客様の口頭での変更やポンチ絵から図面を起こすので、お客様が楽。
- 品質証明書の発行でお客様が安心。
- 取引条件をお客様に合わせる。
- 他
他にもその会社独自のサービスがあるはずです。
新規開拓時にこういったメリットを御伝えする(HPで謳う)だけでも効果があるでしょう。
あらためて自社がお客様にとってどんなサービスを提供しているか考える事が重要です。
QCDを生み出す生産の三要素

QCDを生み出すのは、生産の三要素=3Mと呼ばれる人(Man)・機械(Machine)・材料(Material)です。
さらにメソッド(Method)=方法を加えた4Mが生産の要素と言えるでしょう。
これらの要素がQCDを生み出すので、QCDで確認した強み・弱みも現場まで落とすと4Mで確認する事が出来るでしょう。
現場の改善などを行うときはQCDの弱みから、4Mで現場を確認し大きな問題点を見つけ、原因の追究へと波及させていく事で弱みの克服へとつなげる事ができます。
まとめ
製造業に限らずQCDは付加価値を把握するものとして非常に優れています。
自社の提供しているQCDを見直す事で強み・弱みが見えてくるでしょう。
さらにQCDSのサービスの部分をあらためて確認する事で、自社が当たり前に行っている事にも価値がある事に気付けます。
品質・コスト・納期をそれぞれ別々に捉えていませんか?
QCDを合言葉に自社の強み・弱みを見直して、新たな戦略を立てていきましょう。