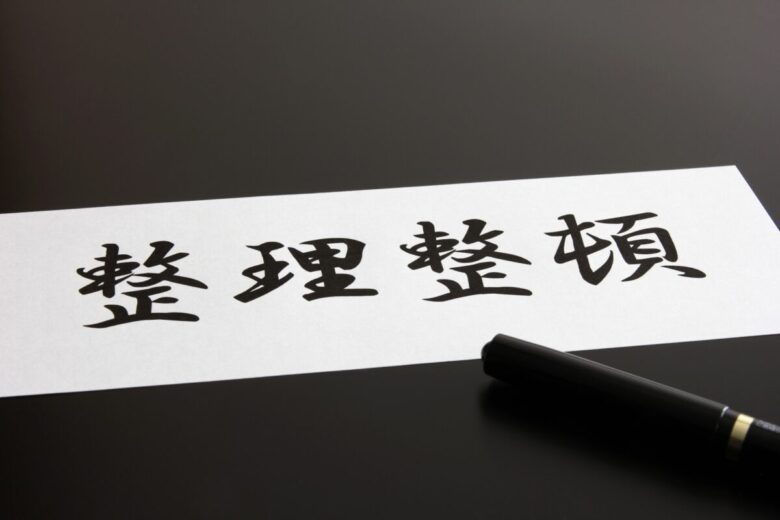整理整頓は製造業の基礎力を高める最も重要な事の一つです。
しかし、整理整頓(2S)が上手くいかず、ご相談頂く事も多いのも事実です。
改めて、整理整頓についてお話していきます。
整理整頓とは
整理整頓という言葉は一般的に使われていますが、その意味を正確に理解されている方が少ないのが現状です。
整理と整頓の意味がごちゃ混ぜになっていたり、ただ単純に片付ける事を言っていたりします。
2Sとは
2Sはまさにこの整理整頓を現場での重要な活動と位置づけて、2S活動などと呼ばれています。
他にも3S・5Sと活動の範囲によって呼び方を変えています。
2Sの意味
2Sは整理整頓の活動です。その中でも、初めて取り組む場合や、5S活動が上手くいっていない場合などに「2Sから始める」といった言葉で使われる事があります。
2Sの目的
2Sの最終的な目的は、ムダをなくし、効率化する事で、工場の利益を最大化する事です。
そして、2S活動を定着化させる事で、現場の意見やモチベーションを引き出す事で、人材活性化を達成するという目的もあります。
整理(seiri)の意味やポイント
整理の意味を改めてお話します。
我々コンサルタントは言葉の意味や定義をとても大切にしています。
言葉の意味がバラバラだと意図した通り伝わらない事があるからです。
工場経営の中で2S活動を推進していくためには現場内で意味の統一を必ず行うようにしましょう。
整理とは「いらないものを捨てる事」

整理とは「いるもの」と「いらないものに分け
「いらないものを捨てる事」です。
非常に単純でありながら、非常に難しい事です。
整理の効果
整理には以下のような効果があります。
- いらないものを捨てることで、スペースが生まれる
- 目に入るモノが減り、探す時間などのムダが減る
- 邪魔なモノが減り、安全性が高まる
- 仕事がしやすい環境となり、集中力が高まるなど、効率化につながる
このように、整理には多くのメリットがあります。
整理はなぜ難しい?
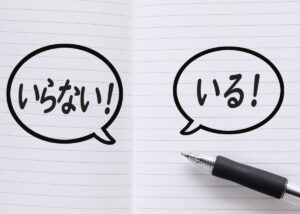
多くのメリットがあるのに、なぜ整理は進まないのでしょうか?
整理が難しいのは「いらないもの」が人によって違うからです。
「整理しましょう!」といっても、人によって整理が進まないのはこのためです。
整理上手はいらないものを的確に決めて実行できます。
一方、整理が苦手な方はこのいらないものを決めれずに、ものを捨てられない状態になるのです。
つまり、大事なのは「いらないもの」とは何なのかを決める事です。
整理=いらないものを決め、いらないものを捨てる

いらないものを決めていくうえでは、「いつ使うのか?」を考えましょう。
いつか使うはほとんど使わないのです。
例えば1年以内に使うのかで考えます。これは事業年度内に使うのかという事でもあります。
事業年度ごとに棚卸をするわけなので、最大でも1年以内として考えると良いでしょう。
しかし、1年以内には使わないけど使う予定がある!という場合も当然あります。
使う予定があるので、いらないものの定義から外れます。
ルールは厳しく決めますが、柔軟に変更する事も重要です。
整理の対象は?

整理の対象は工場の中のもの全てです。
しかし、いきなり一斉に始める事が難しいのが実情です。
エリアを絞って徐々に広げていくのが、通常業務の負担になりにくい方法です。
ただし、会社によっては、みんなでやる事が重要という場合もありますよね。
これは社長の方針次第です。
何事もテクニックだけに頼らず、社長自身の想いを大切に取り組んでいきましょう。
整頓(seiton)とは
整頓とは必要なものが、適切な場所にあり、いつでも、すぐに、誰でも、使える状態である事です。
片付けるという「行為」だけではなく、利益を上げるための「状態」であると認識しましょう。
整頓とは
整頓とは、「いつでも・すぐに・誰でも」使える状態にすることです。
この状態を作るために整頓を行うので、この状態であれば、見た目が悪くても問題ありません。
見栄えだけ良くても中身がなければ意味がありませんので、現場の皆さんと一緒に悩んで作り上げていくものになります。
| 状態 | ポイント・仕組み |
| いつでも | 使った人が必ず同じ場所に戻す。 位置・品目表示・貸出簿など |
| すぐに | 探す手間なく使えるようにする。 場所・位置・品目表示・取りやすい仕切りなど |
| 誰でも | 新人や担当外・お客さんでも分かる。 場所・位置・品目表示 |
整頓の効果
整頓をすることで以下のような効果が期待できます
- 探しているものが素早く発見することができて、探す時間のムダがなくなる
- 正しく戻すことで紛失による無駄な購入が減り、経費の削減につながる
- スペースを効率よく生かすことができて、効率の良いレイアウトにつながる
- モノが見える化されることで教育もしやすくなる
このように整頓には現場を良くする直接的な効果があります。
整頓のポイントは整理の後に行うこと

2S活動における整頓は、整理を行った後でないとすることが出来ません。
整理を行わないと、「いらないもの」が混ざってしまい、いらないものを片付けるという本来の整頓の意味から外れてしまうからです。
それはまさにムダな行為です。
いらないものが沢山ある状態では、適切な場所を確保する事が難しいです。
「場所がない」という工場では「いらないもの」が多くあります。
整理を行い、スペースを生んだうえで、適切な場所を決めていきましょう。
整頓のコツ

整頓を推進するために3定管理という言葉があります。
3定管理では、定位置・低品・定量を管理することで効果的な整頓を実現させることができます。
また整頓は、日常的に続けられる仕組みを作る事がポイントになります。
人によっては片付けが苦手な場合もありますので、出来るだけルールではなく、仕組みで片付けを継続させていく必要があります。
下の記事で仕組みづくりについて紹介していますので、参考にしてください。
2S 整理・整頓を推進するために
整理・整頓を推進するためには以下のようなポイントを抑えることが有効です。
- 改めて、経営者や現場の責任者がキックオフを行い、活動化する
- 作業担当者と責任者を明確にして、担当エリアを定める
- 日常的な変化に対応するため、チェックシートなどで実施のチェックを行う
- 定期的に発表を行い、頑張りを周知したり、アイデアを横展開させる
キックオフなどで明確に号令をかけて、変えることの抵抗をなくすことが重要です。
責任範囲を明確に自分ごととして捉えられるようにして、現場を巻き込みながら進めることが必要です。
日常的にモノは増えたり・減ったりする変化をチェックシートなどでしっかりと捉えて、日常的に改善を続けていきましょう。
発表の場を設けて、頑張りを認めてもらうとモチベーション維持につながります。
また、せっかくのアイデアを会社に浸透させるために、横展開の工夫をしていきましょう。
整理整頓が上手くいくと物を減らしたい心理が働く
整理整頓を続けていく事で、物が増えたら減らしたいという心理が働くようになります。
ここまでくれば、2S活動はバッチリです。
現場が自らいらないものを決め、処分する「整理」を行い、より良い場所に、より良い方法で置く「整頓」を行ってくれます。
まとめ
2S活動はムダをなくし、効率化する事で工場の利益を最大化してくれます。
現場改善の基礎となるため、まず最初に2Sから始めるのが良いでしょう。
2Sを通じて人材の活性化も期待できます。
現場が自ら考え、行動するように2S活動も工夫していくと良いでしょう。