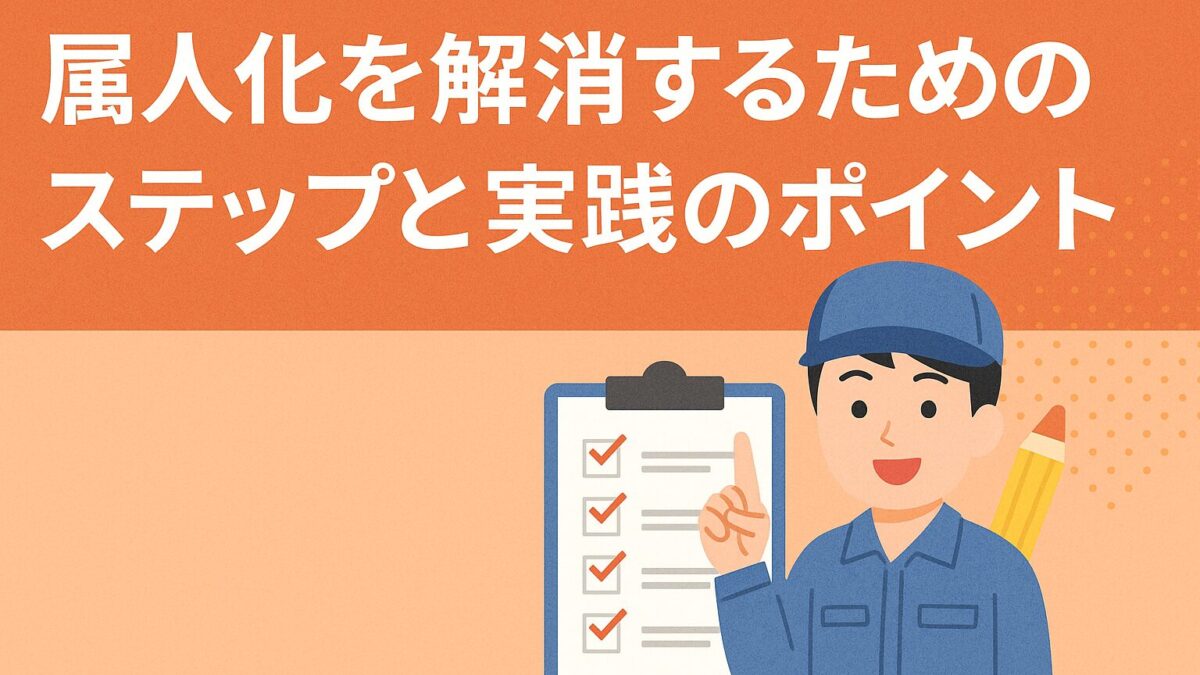造現場でよく聞く悩みの一つに「この作業はあの人しかできない」という属人化があります。表面的には業務が回っているように見えても、担当者の休職や退職、急な配置転換があると一気に混乱が生じ、品質や納期に大きな影響を及ぼします。
私がこれまで支援してきた町工場でも、ベテラン一人に依存していたために新規案件を受けられなかったり、不良が増えてクレーム対応に追われたりするケースを多く見てきました。属人化を放置すると、現場だけでなく経営全体にリスクが波及してしまいます。
本記事では、現場出身コンサルタントの視点から、属人化を解消するためのステップを分かりやすく整理し、実際の支援先で有効だった工夫も交えながら、すぐに実践できるポイントを紹介します。
属人化は、単に「誰かが忙しい」だけでなく、品質・納期・コストすべてに影響を与えます。
原因を掘り下げるためには なぜなぜ分析 のような手法が役立ちます。
属人化を解消するための基本ステップ
属人化の解消には、「思いつきの改善」ではなく、順序立てたステップが必要です。作業を棚卸し、標準化し、教育を通じて共有し、最後に定着を図る。
この一連の流れを継続的に回すことで、初めて組織としての力が底上げされます。ここでは、現場で実際に効果を上げている4つのステップを紹介します。
現状の見える化(作業の棚卸し)
最初の一歩は「どの作業が誰に依存しているか」を把握することです。
支援先でも、作業の流れを洗い出すと「Aさんしか操作できない機械」「Bさんだけが持っている顧客対応ノウハウ」といった属人化ポイントが必ず出てきます。
これを見える化することで、改善の優先順位が明確になり、経営者やリーダーも「どこにリスクがあるか」を共有できます。
特定の人だけが判断している場合、不良が発生しても再現や改善が困難になります。
そこで重要になるのが QC七つ道具による「見える化」 です。
詳しくは QC七つ道具の活用方法 をご覧ください。
標準化(作業手順の文書化・チェックリスト化)
棚卸しで見つけた属人化作業は、標準化に移行します。作業手順を文書化し、チェックリストや動画で残すことで、誰がやっても同じ品質・スピードで進められるようになります。
ただし、標準化は「作っただけ」では形骸化しやすいものです。支援先では、実際に新人や他のメンバーに手順を試してもらい、現場で本当に使えるレベルまで修正を重ねています。
教育と共有(OJT・クロストレーニング)
標準化した内容を、教育を通じて全員に広げることが次のステップです。OJTやクロストレーニング(多能工化)を進めることで、「特定の人しかできない」状態を徐々になくしていけます。
実際の支援先でも、2人1組で作業を入れ替える練習を取り入れるだけで、短期間で属人化が大きく改善しました。教育を仕組みとして組み込むことが重要です。
定着と改善(評価仕組み・フィードバック)
最後に大切なのが、属人化解消の仕組みを定着させることです。単発の研修や改善活動ではすぐに元に戻ってしまいます。
評価制度に「標準化の活用」や「後輩指導」を組み込み、定期的にフィードバックを行うことで、改善が組織文化として根付いていきます。
支援先でも、月次で「改善共有ミーティング」を設けたことで、現場メンバーが主体的に改善を進める文化が生まれました。
実践で押さえるべきポイント
属人化解消のステップを踏むだけでは、現場に根付かないケースもあります。
実際の製造現場では、標準化が形骸化したり、特定工程だけ属人化が残ったりといった課題が出てきます。ここでは、支援先で多く見られた注意点と、それを克服する工夫を紹介します。
「標準化の形骸化」を防ぐ工夫
マニュアルや手順書を作っても、現場で活用されなければ意味がありません。
支援先では、手順書を単なる資料として棚にしまうのではなく、「実際に作業を行いながらチェックできる形」に工夫しました。
例えば、写真入りの作業シートや、タブレットで確認できる動画マニュアルを導入することで、日常的に活用される仕組みへと変わりました。
属人化が進みやすい工程の特徴
属人化は「段取りが複雑」「品質に直結する重要工程」「顧客とのやり取りが必要」といった部分に集中しやすい傾向があります。
支援先の例でも、金型交換や検査工程、特殊な顧客対応などに偏っていました。まずはこうした工程に焦点を当てることで、改善の効果が大きく出やすくなります。
支援先で効果的だった取り組み事例
ある工場では、属人化していた検査工程を標準化するために、測定条件と判定基準を整理し、チェックリスト化しました。
その結果、新人でも判断に迷わず作業できるようになり、ベテランの負担が大幅に削減されました。
また、別の支援先では、ベテラン作業者のノウハウを動画で記録し、教育の場で繰り返し使えるようにしたことで、短期間で属人化を解消できました。
属人化解消がもたらす効果
属人化の解消は、単に「誰でも作業できるようになる」ことに留まりません。
品質、納期、コストといった経営に直結する成果をもたらし、組織全体の安定と成長につながります。ここでは代表的な3つの効果を整理します。
品質安定と不良削減
属人化が解消されると、作業手順が標準化されるため品質が安定します。
支援先でも「ベテランと新人で不良率が大きく違う」といった状況が改善され、不良が減少しました。
特に「検査の属人化」を解消した工場では、新人の工程内不良が20%以上削減され、顧客からのクレームも激減しました。
納期遵守率の向上
特定の人に依存していると、急な休職や多忙で作業が滞り、納期遅れにつながります。
属人化を解消することで、誰でも工程を回せる状態になり、突発的なトラブルにも対応できるようになります。
支援先のある企業では、納期遵守率(納期調整含む)が80%から95%へ改善し、さらなる案件の獲得にもつながりました。
工程が人に依存していると、欠勤や異動で納期遅延が発生します。
改善の枠組みとして PQCSMEで考える現場改善 を取り入れると効果的です。
チーム力の底上げと離職リスク低減
属人化を解消すると、チーム全体で仕事を分担できるため、個人の負担が減り、働きやすい環境が整います。
結果として、離職リスクが低下し、組織力が向上します。実際に支援先では「一部のベテランが抱え込んでいた仕事が分散され、若手が成長するきっかけになった」という声が多く聞かれます。
これは人材育成や後継者づくりにも直結する効果です。
属人化を解消するには、標準化と教育の仕組みを「回し続けること」が欠かせません。
その際の基盤となるのが PDCAの実践 です。
まとめ
属人化は、中小製造業にとって「見えているのに手を打てていない課題」のひとつです。
放置すれば品質トラブルや納期遅れを招き、経営全体に大きなリスクを与えます。しかし、順序立てたステップで改善を進めれば、確実に解消することができます。
本記事で紹介した
- 現状の見える化
- 標準化
- 教育と共有
- 定着と改善
という流れは、私が支援先で実際に成果を上げてきた方法です。
属人化の解消は、単なる効率化ではなく、品質安定や納期遵守率の向上、そしてチーム力の底上げにつながります。
経営者にとっても、安定した組織運営と次世代育成の基盤となります。
「その人しかできない仕事」を減らし、「誰でもできる仕組み」を整えること。
これが現場改善の本質であり、持続的に成長できる組織をつくる第一歩です。
あわせて読みたい関連記事:
なぜなぜ分析で原因を突き止める方法
QC七つ道具を使った改善事例
PQCSMEで考える現場改善の視点
なぜPDCAは回らないのか?現場で陥りやすい落とし穴と解決策