QC工程表はどのような目的で使用するのか、作成方法や使い方をご紹介します。
メール登録でExcelのテンプレートをプレゼントいたしますので、是非活用頂ければと思います。
QC工程表(工程図)とは
QC工程表は英語で「Quality Control Chart」原材料などの調達から、製品の生産、出荷までの
一連のプロセスを図表にしてまとめたものです。
日本品質管理学会は以下のように定義をしています。
製品・サービスの生産・提供に関する一連のプロセスを図表に表し,このプロセスの流れに沿ってプロセスの各段階で,誰が,いつ,どごで,何を,どのように管理したらよいかを一覧にまとめたもの
一般社団法人日本品質管理学会
図表に表すだけでなく、各段階で、だれが、いつ、どこで、何を、どのように管理すべきかが一覧にまとめてある表ですので、生産全体を把握する事に長けています。
QC工程表の役割
QC工程表には以下のような役割があります。
- 製造の全体像を把握する事が出来る。
- 各工程の管理方法をまとめる事で、品質不良が出ないように出来る。
- 万が一品質不良が出た場合は、その原因を見つける事が出来る。
- 各工程の問題点発見や品質不良削減のきっかけとなる。
- 品質管理につながる情報を現場へ周知できる。
- 作業標準書作成の基準となる。

ISOのためだけじゃない!QC工程表の目的
QC工程表の基本的目的は以下のような事であると考えます。
- 品質に対するお客様満足の向上
- 製造プロセスの改善
- 現場力の向上

QC工程表を導入されている企業の多くは、ISO取得のためのものとして認識されている場合があります。
ですが、本来はお客様満足の向上や、製造プロセスの改善、現場力の向上など、当社全体の品質のレベルアップに使うことのできるとても重要な資料となります。
品質に対するお客様満足の向上
お客様が満足する品質を提供するために品質管理を行うわけなので、お客様の満足度が上がらなければ意味がありません。
そのためには、品質工程表を外部への説明資料として活用することが求められます。
営業がお客様への説明資料に活用することや、クレームへの対応として、品質管理の改善を示す場合など、
信頼獲得に大きな効果があると考えます。
QC工程表をそのまま使うのではなく、お客様の求める部分に対して抜粋して使うことが望ましいと考えます。
製造プロセスの改善
また、QC工程表には各工程の製造に関する多くの情報が記載されるため、それにより製造プロセスそのものが改善出来れば、コスト削減や短納期化にもつながっていきます。
QC工程表で製造プロセス全体を把握しながら、改善が必要な点を深堀りを行って、プロセス改善をしていきましょう。
現場力の向上
製造プロセスを改善する癖を現場が手に入れる事で、現場力が上がり、問題に早く気づき、原因を特定でき、改善を実行できる人材が育ってきます。
現場が成功体験を積んでいくことで自律的な改善につながっていきます。
QC工程表から問題定義していくことで、全員が理解しやすく、成功しやすくなることがメリットです。
QC工程表と作業標準書の違い
QC工程表と作業標準書の違いについては、QC工程表が全体像、作業標準書が詳細という違いがあります。
QC工程表では特に品質管理特性や方法などが記載されているのに対し、
作業標準書はQC工程表の管理項目や・管理基準を満たすように作業方法を標準化するためのものです。
ですので、作業標準書を作る前にQC工程表を作る事をおすすめします。
QC工程表をもとに作業標準書を作成する事で、品質を維持できる作業を標準化する事につながります。
作業標準書(手順書)を作成する方は下の記事も参考にしてください。
QC工程表の内容
QC工程表の特徴的な内容は工程記号・管理点・管理方法などを記載する事です。
工程名
工程名を記載します。イメージは作業名です。
実際に行われる穴あけ加工や組み立てといったもので、すぐに作業内容がイメージできるようにしてください。
工程記号
工程記号は上の工程が実際にどんな状態、行動なのかを明確に出来るものです。
こちらは工程改善の時も使用しますので、すぐに使えるようExcelシートに用意しておきます。
Excelで記号が入力できず図で処理する事が多いですが、私が認定を頂いている生産性本部の記号であれば、文字として変換可能ですので、便利です。
*()は、日本生産性本部独自の記号の使い方
| 工程名称 | 工程記号 | 内容 |
|---|---|---|
| 加工 | 加工とは、ワーク(製品)に形状・性質に物理的・化学的変化を与える状態 | |
| 数量検査 | 数量検査とはワーク(製品)の数・量をはかり、その結果を基準と比較して合否を判定すること | |
| 品質検査 | 品質検査とはワーク(製品)の品質特性をはかり、その結果を基準と比較して合否・適否を判定すること | |
| 貯蔵 | 貯蔵とは原料、材料、部品などが計画的に保管されている状態 | |
| 滞留 | 滞留とはワークがある場所で加工や検査が行われていないで停止している状態 | |
| 運搬 | 運搬とはワーク(製品)がある位置から他の位置へと移動されている状態 |
管理項目
管理特性と品質特性を合わせて管理項目としています。
管理特性と品質特性は要因と結果といった関係性を持っています。
管理特性=あらかじめ設定しておく加工条件(要因)
品質特性=管理特性で加工した結果の数値で表させる公差や数値の範囲
管理方法
管理方法では以下の内容を記載します。
- 検査方法=どのように測定するのか?
- 検査頻度=全数や抜取の頻度・2回/日などのタイミングなど
- 検査機器=何で検査するのか?
- 担当者=誰が?
- 責任者=誰が?
QC工程表のフォーマット
私が使用しているQC工程表のExcelフォーマットです。
ダウンロードしてお使いください。
*フォーマットでは使いやすいようにリストで工程記号を選択できるようにしてあります。
そのため生産性本部方式の工程記号を使用しています。
QC工程表の作り方(項目の記入方法)
QC工程表を作成するには上記のようなフォーマットを使用し、各項目を埋めていく事となります。
フローチャート作成
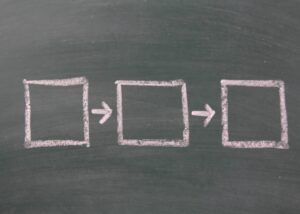
まずは工程内の作業を洗い出し、フローチャートをつくります。
フローチャートでは工程記号を割振り、製品にどんな変化・影響を与えているかをわかるようにします。
担当者を集めホワイトボードを使って、付箋に工程の流れや注意している点などを書いてもらい、適切な位置に貼っていくと簡単に濃い情報が集まってきます。
管理特性

次に管理特性を記入していきます。
管理特性は加工条件だと考えられます。
その作業を行う際のドリルの回転数やはんだごての温度など、品質を安定させる加工条件です。
これは「つくりこみの品質」であり、加工条件を突き詰めていく事で、品質を一定に早く、安く作る事につながります。
作業標準書を連動させるためには、こちらに作業標準書のNo.も記載しておきます。
そうする事で、全体の把握と、そこから詳細の作業標準書へと追跡していく事ができます。
品質特性

一方の品質特性は、その結果であると考えます。
加工条件通り加工した際の「出来ばえの品質」であるため、加工条件が悪ければ出来ばえが悪くなり、出来ばえの品質がお客様の望む品質と合致しなければ、いつまでたってもクレームはなくなりません。
品質特性に記入されるのは、寸法や色など、工程内検査での判定基準です。
どこをチェックするのかといった言葉が入るものと思ってください。
当然この工程内検査で合格しなければ、次の工程に送ってはいけません。
管理方法

管理方法では、管理基準を決めます。品質特性に記載されたチェック箇所に対する寸法値・公差・トルク・技術者のレベルや、視力・温度など数字として表せるようにして記入していきます。
これにより、品質特性の数字的根拠を得る事になります。
検査方法

検査方法では、温度計やトルクレンチ、ノギスといった検査機器や、目視といった方法などを記載します。
ノギス等校正が必要なものであれば、そのNo.なども記載しておくことで、検査機器による不具合もなくしたり、追跡したりすることができます。
検査頻度
次の検査頻度では、製品検査に対しては、全数なのか抜き取りなのかが大きな違いとなります。
また、炉の温度の管理基準であれば、炉の温度を1日に何回チェックするのかといった書き方になります。
担当者と責任者
そして担当者、責任者を記載していきます。
担当者、責任者名を直接記載しても良いですし、作業者、班長(リーダー)といった役職で記載しても良いかと思います。
次の検査記録では直接記入するわけではなく、検査記録を記入する帳票の名称を記載しておきます。
そのため、帳票の方で個人名が記入されますので、上記の担当者の詳細も追跡する事が出来ます。
異常時の処置
最後に異常時の処置について、あらかじめ決めておく事が重要です。
まずは品質異常が発生した際に誰に報告するのか、責任者や担当部署を記載しておくと良いでしょう。
作業者が異常の処置も行う場合は、異常処理方法や、異常処理に使う資料のNo.を記載しておくことで、異常への対処方法まで追跡する事が可能となります。
まとめ
QC工程表の役割た使い方について説明しました。
QC工程表は全体像を把握できる非常に優秀なものであり、製造プロセスの勘所を示す事が出来ます。
勘所をさらに突き詰める改善や、品質にばらつく箇所の加工条件や検査方法を見直すきっかけを作る事も出来ます。
メール登録でフォーマットをダウンロードできますので、是非使って改善や管理に役立ててください。




