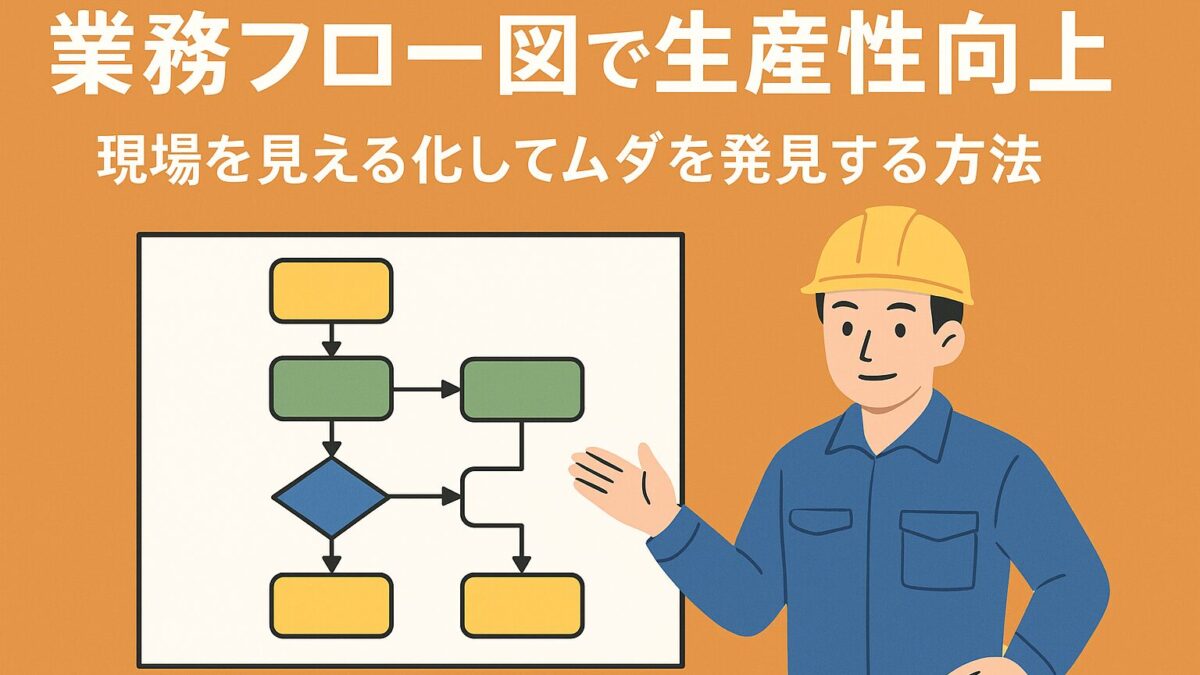「なぜこの工程は時間がかかるのか?」「どこでムダが発生しているのか?」――そんな疑問を解決する手助けとなるのが業務フロー図です。
業務フロー図は、作業や工程の流れを図式化して見える化する方法です。複雑な現場の流れを整理することで、ムダや停滞のポイントを発見しやすくなります。
本記事では、業務フロー図の基本から作り方、改善への活用方法までをわかりやすく解説します。現場出身コンサルとしての経験を踏まえ、実際に生産性向上につながる使い方を紹介します。
業務の流れを整理して見える化することは、生産性向上の第一歩です。
生産性向上とは?製造業の現場で実現するためのポイント
業務フロー図とは?
業務フロー図とは、業務や工程の流れを図式化して見える化する手法です。
製造現場では「工程フロー図」や「作業フロー図」と呼ばれることもあり、誰が・何を・どの順序で進めるのかを一目で理解できるように表します。
属人化を防ぎ、誰でも同じ流れで作業できるようにする視点とも深くつながります。
属人化とは?中小製造業に潜むリスクと解決策
現場で使う目的
- 複雑な業務を整理し、関係者全員で共有しやすくする
- 作業のムダや停滞を発見しやすくする
- 部署や人をまたいだ業務のつながりを把握する
業務フロー図で表せる一例
- 受注管理:顧客からの注文や見積の内容を整理し、契約情報とあわせて管理する段階
- 生産計画:注文数量や納期と自社の能力を照らし合わせ、無理のない計画を立てるプロセス
- 生産指示:計画を現場に落とし込み、工程ごとの作業指示や資材の手配を行うステップ
- 出庫管理:在庫や資材を出庫する準備を行い、担当部門へ確実に引き継ぐ流れ
- 出荷管理:出荷済み製品の数量・納期・顧客情報を記録し、トレーサビリティを確保する工程
このように業務フロー図は、日々の仕事の流れを整理して見える化することで、改善の出発点を見つけるために活用できます。
まずは全体の業務フローを作り、各工程の詳細について、業務フロー図に落とし込んでいくことがおすすめです。
業務フロー図を活用するメリット
業務フロー図は、単に作業の流れを絵にするだけではありません。現場で活用することで、改善や人材育成に直結するさまざまな効果があります。
ムダや停滞を発見しやすい
作業や工程を一つひとつ可視化すると、手戻りや待ち時間、余分な移動といったムダが明確になります。これにより改善の優先順位をつけやすくなります。
業務の標準化につながる
作業の流れを明示することで、誰が見ても同じ手順で業務を理解できるようになります。結果として属人化を防ぎ、新人教育や多能工化の基盤としても役立ちます。
業務フロー図は標準化や教育にも役立ちます。多能工化とあわせて考えると効果が高まります。
製造現場の多能工化とは?生産性を高める進め方と実践ポイント
部署間の連携を強化できる
部門をまたぐフローを示すことで、「どこで情報が止まりやすいか」「引き継ぎが不十分になりやすいか」を確認できます。全体最適を意識した改善に直結します。
改善の成果を共有しやすい
業務フロー図は現場ミーティングや改善提案の場でも活用できます。改善前後を比較して図示すれば、成果が一目で伝わりやすく、現場全体の納得感も高まります。
業務フロー図の作り方
業務フロー図を効果的に使うためには、最初に目的と対象を明確にすることが大切です。そのうえで、現場の実態を把握しながら段階的に整理していきます。
1.作成の目的を明確にする
2.対象業務と対象者を決める
3.部署や担当範囲を明確にする
4.業務の流れを洗い出す
5.図式化する
1. 作成の目的を明確にする
改善に使うのか、教育に使うのか、あるいは部署間の情報共有に使うのか。目的を決めることで、図に盛り込む内容や粒度が変わります。
2. 対象業務と対象者を決める
どの業務をフロー化するのか、そして誰に見せるのかを明確にします。経営層への説明資料なのか、現場教育用なのかによって構成も変わります。
3. 部署や担当範囲を明確にする
工程ごとに「どの部署」「どの担当者」が関与するのかを整理します。責任や役割が曖昧な部分は問題が見つかりやすく、改善のヒントになります。
4. 業務の流れを洗い出す
現場観察やヒアリングを通じて、実際の業務手順を一つひとつ抽出します。机上の想定ではなく、現場の実態をもとに整理することが重要です。
実際に担当者にヒアリングしてみると、不自然に追加された作業などが見つかるケースがあります。
突発的な問題に対処した際に追加した作業が、その問題が解消された後も残ってしまっていたり、当時の担当が、自分流にアレンジしていたりすることがあるからです。
5. 図式化する
洗い出した内容をフローチャートや工程図として図式化します。見やすさを優先し、複雑にしすぎないことが活用のカギです。
登場人物・もしくは部署を左側、もしくは上部に記載します。
そのうえで、時系列に並べていく事になります。
登場人物などを左側に記した場合は、左側から右側へと、フローを図式化します。
特に、ホワイトボードなどで横長に展開した方が見やすいケースではこちらがおすすめです。
登場人物を上側に記した場合は、上から下へとフローを図式化します。
特に最初からエクセルなどで展開していく場合はこちらの方が書きやすいかもしれません。
私は、ホワイトボードを使って、図式化していくことが多いため、左側から右へと展開する方法を採用しています。
業務フロー図を改善に活かす方法(応用編)
業務フロー図は、描いただけでは意味がありません。改善にどう活かすかが重要です。ここでは現場での応用的な使い方を紹介します。
改善の出発点として使うなら、原因追及の仕組みと組み合わせるのがおすすめです。
現場で使える!なぜなぜ分析の進め方とコツ|仕組みで再発防止する方法
問題点を洗い出す
フロー図を見直すと、手戻りや待ち時間、責任の所在が曖昧な部分が浮かび上がります。まずは「どこにムダが潜んでいるか」を洗い出すことから始めましょう。
良くあるのはダブりのチェックなどです。
また、工程間や担当者間の行き来が多い場合もムダがある可能性が高まります。
改善テーマを抽出する
見つかった課題を「すぐに解決できるもの」「時間やコストがかかるもの」に分けて整理します。優先順位をつけることで、改善活動が現実的に進めやすくなります。
ただし、解決策については、大胆なもの、大がかりなものを除外せず、検討課題に載せるようにしましょう。
将来的な解決に向けて、継続的に議論していくことも大切です。
改善前後を比較する
改善案を反映した新しいフロー図を作り、現場に共有します。前後比較を行えば効果が一目で伝わりやすく、現場の納得感も高まります。
上司に説明するときも、非常に分かりやすく、稟議が通りやすくなるはずです。
教育や定着に活用する
改善後のフロー図を教育ツールとして活用すれば、新人育成や多能工化の推進にも役立ちます。「改善して終わり」ではなく、継続的な教育・標準化に活かすことが大切です。
フロー図を見る事で、新人も流れをイメージしやすくなります。
教育にあたっては、フローの中での教育担当者なども追記しておくと、新人が困ったときに相談相手が明確になります。
業務フロー図を活用する際の注意点
業務フロー図は便利なツールですが、使い方を誤ると形骸化してしまいます。効果を発揮させるために、次の点に注意しましょう。
複雑にしすぎない
あれもこれも詰め込みすぎると、誰も読まない図になってしまいます。改善や共有に必要な情報に絞り、見やすさを優先することが大切です。
目的に合わせて精査しましょう。
現場の声を反映する
机上で作成しただけのフロー図は実態と乖離しやすく、信頼されません。必ず現場観察や担当者ヒアリングを行い、実態に即した図に仕上げましょう。
特に現場担当者を作成に参加させると、巻き込みながら進める事が出来ます。
定期的に更新する
業務は常に変化しています。フロー図を作って終わりにせず、定期的に見直して最新化することが必要です。古いフロー図は改善の妨げになる場合もあります。
多くの改善の障壁が、「前の人に教わった方法だから」「昔からこの方法だから」といった思考の停止です。アップデートしていくことで、改善につながっていくはずです。
部署間の認識差に注意する
同じ工程でも、部署や担当者によって「やっているつもり」「依頼したつもり」といったズレが発生しがちです。フロー図を使って共通認識を作ることを意識しましょう。
特に業務の責任が不明確な場合はフロー図の中で、明確化していきましょう。
まとめ
業務フロー図は、製造現場の生産性向上に直結する有効なツールです。工程や業務の流れを「見える化」することで、ムダや停滞を発見し、改善活動の出発点を作り出せます。
本記事では、業務フロー図の基本からメリット、作り方、改善への活用方法、注意点までを解説しました。要点を整理すると次の通りです。
- 業務フロー図=作業や工程を図式化し、共有や改善に活かすツール
- メリット:ムダの発見、標準化、部署間連携強化、改善成果の共有
- 作り方:①目的を明確化 → ②対象業務と対象者を決定 → ③部署や担当範囲を整理 → ④流れを洗い出す → ⑤図式化する
- 応用編:問題点を洗い出し、改善テーマを抽出 → 改善前後を比較 → 教育や定着に活用
- 注意点:複雑化しすぎない、現場の声を反映、定期的な更新、部署間の認識差に注意
業務フロー図は「描いて終わり」ではなく、活用して初めて価値が生まれます。ぜひ自社の現場で取り入れ、改善と教育の両面で役立ててみてください。
業務フロー図は他の改善手法と組み合わせることで、より効果を発揮します。
QC七つ道具をどう使う?製造現場で役立つ実践事例