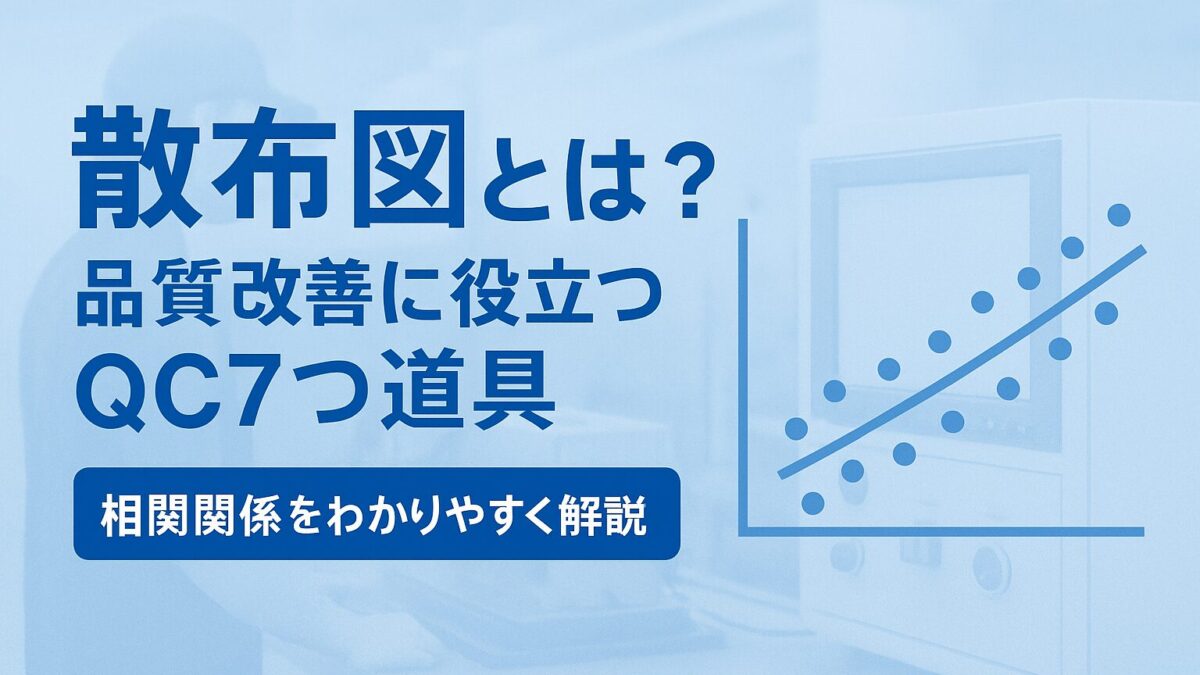品質トラブルの原因を探る際、「どの要因とどの結果が関係しているのか」を明確にすることは欠かせません。
散布図は、こうした要因間の関係性(相関)を見える化するQC七つ道具の一つです。
縦軸と横軸に異なるデータをプロットすることで、2つの要素の間にどのような傾向があるかを一目で把握できます。
例えば、「加工時間と寸法誤差」「温度と不良率」といった関係を散布図で確認すれば、
感覚ではなくデータに基づいた原因特定と改善策の立案が可能になります。
本記事では、散布図の基本的な仕組みから作り方、品質改善への活用方法までを、
製造現場出身のコンサルの視点でわかりやすく解説します。
散布図とは
散布図は、2つのデータの間にどのような関係があるかを視覚的に把握するためのグラフです。
縦軸と横軸に異なる要素を取り、測定データを点としてプロットすることで、
「一方が変化するともう一方も変化するのか?」を直感的に理解できます。
品質改善においては、原因と結果の関係を明確にし、勘ではなくデータに基づいた判断を行うために活用されます。
2つのデータの関係を視覚化するグラフ
散布図は、例えば「加工時間と寸法誤差」「温度と不良率」「作業者経験年数と作業時間」といった、
**要因と結果の関係性(相関)**を見える化するために使います。
点の分布に傾向が見られれば、2つの要素に何らかの関連があると判断できます。
一方で、点がランダムに散らばっていれば、関係性が弱い、または存在しないと考えられます。
QC七つ道具の中での位置付け
散布図は、QC七つ道具(パレート図、特性要因図、ヒストグラム、管理図、散布図、チェックシート、グラフ)の中でも、
要因と結果の関係を「見える化」するための分析ツールとして位置付けられています。
パレート図やヒストグラムが「どの要因に注目すべきか」を示すのに対し、
散布図は「その要因と結果にどのような関係があるのか」を明確にします。
工程改善や品質安定化の過程で、他のツールと組み合わせて使うことで、より精度の高い分析が可能になります。
散布図を使う目的と効果
散布図を使う目的は、要因と結果の関連性を可視化して、改善の方向性を見つけることです。
データを視覚的に整理することで、「作業条件が変わると不良が増える」「温度上昇で寸法が拡大する」といった傾向を発見できます。
また、相関関係を確認することで、重点的に対策すべき工程条件や管理項目を特定することができます。
このように散布図は、問題の原因追及や再発防止策の立案において、現場で非常に有効なツールです。
なお、散布図はあくまで相関関係を確認するためのツールであり、
「要因と結果の因果関係」を直接証明するものではありません。
見た目に関係がありそうでも、実際には別の要因が影響している場合もあります。
そのため、散布図で関係性を見つけた後は、特性要因図やなぜなぜ分析で裏付けを取ることが重要です。
QC七つ道具の全体像や他のツールの位置付けについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
→ QC七つ道具とは?種類・使い方・事例をわかりやすく解説
散布図の作り方
散布図は、数値データを整理してグラフに落とし込むだけで簡単に作成できます。
重要なのは、正確なデータを選び、要因(X軸)と結果(Y軸)を明確に区別することです。
ここでは、現場でよく使われる例をもとに、基本的な作り方を順を追って説明します。
① データを2種類用意する(要因と結果)
まず、分析したい「要因」と「結果」のデータをそれぞれ用意します。
たとえば、
- 加工時間(要因)と寸法誤差(結果)
- 温度(要因)と不良率(結果)
- 作業者経験年数(要因)と作業時間(結果)
など、一方の変化がもう一方に影響しているかもしれない関係を想定して選定します。
データ数は少なすぎると傾向がつかみにくいため、最低でも20点以上あると望ましいです。
② データをグラフ上にプロットする
横軸に「要因(原因となる項目)」、縦軸に「結果(影響を受ける項目)」を取り、
対応するデータを点でプロットしていきます。
例えば、「温度」と「不良率」の関係を調べる場合は、温度を横軸、不良率を縦軸にして、
それぞれの測定結果を一つひとつの点として描きます。
この段階では、点を結んだり平均線を引いたりする必要はなく、データの分布パターンをそのまま確認するのが基本です。
③ 点の分布傾向を確認して関係性を判断する
プロットした点の配置を観察し、どのような傾向があるかを確認します。
点が右上がりの方向に並んでいれば「正の相関」、右下がりであれば「負の相関」と判断できます。
もし点がランダムに散らばっていれば、2つの項目の間に明確な関係はないと考えられます。
また、明らかに他と離れた点(外れ値)がある場合は、測定ミスや特殊な条件が影響している可能性があるため、別途確認が必要です。
散布図で関係をつかんだあとは、ヒストグラムでデータのばらつきを確認すると理解が深まります。
→ ヒストグラムとは|品質のばらつきを見える化するQC7つ道具の基本
散布図の形と意味
散布図の魅力は、データの分布形から2つの項目間の関係性を直感的に読み取れることにあります。
ここでは、代表的な分布パターンと、それぞれが示す意味を整理します。
正の相関(要因が増えると結果も増える)
点が右上がりに分布している場合、一方の値が増えるともう一方も増える関係があると考えられます。
例えば、「作業時間が長くなるほど仕上げ精度が向上する」や「温度が高いほど反応速度が上がる」といったケースです。
このような関係を正の相関と呼びます。
ただし、相関があるからといって必ず因果関係があるとは限らず、別の要因が関与している可能性もあります。
負の相関(要因が増えると結果が減る)
点が右下がりに並んでいる場合は、一方が増えるともう一方が減少する関係があると考えられます。
たとえば、「設備稼働時間が長いほど不良率が上がる」や「温度が高いほど製品寿命が短くなる」といった例です。
このような関係を負の相関と呼び、工程条件の過剰・不足を見極める際に役立ちます。
相関がない場合(関係が見られない)
点が全体にばらばらに散らばっている場合、2つの項目に明確な関係は見られないと判断します。
ただし、「見かけ上の無相関」はデータの範囲設定や測定精度が原因のこともあります。
分析範囲を広げたり、条件を変えて再度データを取ると、関係が見えてくる場合もあります。
例外点(外れ値)の確認
散布図の中で、他の点から大きく離れているものは**外れ値(例外点)**です。
これらは測定ミス、記録漏れ、または特殊な条件(材料ロットや設備異常など)によって生じることがあります。
外れ値をそのままにしておくと、全体の相関関係を誤って評価してしまうことがあるため、
原因を確認した上で、データとして除外するか、別途要因分析を行うかを判断することが重要です。
散布図の活用例
散布図は、工程や品質データの関係を整理し、改善の方向性を見極めるための強力な分析ツールです。
ここでは、製造現場で実際に使われる代表的な3つの活用例を紹介します。
加工条件と寸法精度の関係分析
加工条件が変わることで、製品寸法の精度にどのような影響が出ているかを調べる際に散布図は有効です。
たとえば、切削速度や送り速度を横軸に、加工後の寸法誤差を縦軸に取ることで、
条件設定によって誤差が拡大する傾向や、一定範囲内で安定している範囲を把握できます。
これにより、最適な加工条件の見極めや、設備・治具の調整指針を得ることが可能です。
温度・湿度と不良率の関係把握
環境条件が品質に影響する工程では、温度や湿度と不良率の関係を散布図で確認することで、
品質変動の要因を特定できます。
例えば、成形工程や塗装工程などでは、温度が高すぎると気泡や剥離が増えるなどの傾向が見られる場合があります。
データを継続的に記録することで、品質が安定する環境条件の最適範囲を導き出すことができます。
設備ごとの傾向比較と改善テーマ設定
同じ製品を複数の設備で製造している場合、それぞれのデータを散布図で比較することで特徴が見えてきます。
A設備では点が右上がりに、B設備ではばらつきが大きいなど、設備特性や精度の違いが明確になります。
この結果をもとに、標準化の推進や教育テーマの設定につなげることで、
全体としての工程安定化や品質ばらつきの縮小を図ることができます。
散布図を使う際の注意点
散布図は視覚的に分かりやすく、分析の入口として非常に有効ですが、
使い方を誤ると誤った結論を導いてしまうこともあります。
ここでは、現場でよく起こる注意点を整理し、信頼性の高い分析を行うためのポイントを解説します。
データの数が少ないと誤解を招く
散布図の精度は、データの量と質に大きく左右されます。
点が少ない状態では偶然の分布に見えてしまい、実際の傾向を正確に判断できません。
最低でも20点以上、できれば30点以上のデータを取ることで、
ばらつきの傾向や相関関係を安定的に把握できます。
見た目の相関と因果関係は別問題
散布図で相関が見られても、それが必ずしも「原因と結果の関係」を意味するとは限りません。
例えば、「室温と作業者の集中度」に相関が見えても、実際には作業環境の照明や時間帯など
他の要因が影響している可能性があります。
散布図で傾向を掴んだ後は、特性要因図やなぜなぜ分析を用いて裏付けを取ることが大切です。
(→ 特性要因図(フィッシュボーン図)とは?意味・書き方・例を徹底解説)
異常値(外れ値)をそのままにしない
他の点から大きく離れたデータ(外れ値)は、分析結果をゆがめる原因になります。
測定ミスや一時的な条件変化など、明らかな理由がある場合は除外し、
理由が特定できない場合は「別の要因が関係している可能性」として調査対象に加えることが重要です。
外れ値の扱い方次第で、相関関係の見え方が大きく変わるため注意が必要です。
まとめ
散布図は、2つのデータの関係性を見える化し、品質の変動要因を客観的に把握するための基本ツールです。
QC七つ道具の中でも、要因と結果のつながりを分析する際に欠かせない存在であり、
現場で発生している現象を「感覚」ではなく「データ」で理解するための第一歩となります。
また、散布図で相関関係を確認したあとは、
特性要因図やなぜなぜ分析などを活用して、根本原因の特定と再発防止へとつなげることが重要です。
散布図は、単なるグラフではなく、**現場が問題の本質に気づくための“見える化ツール”**として活用することで、
改善活動の質を大きく高めることができます。