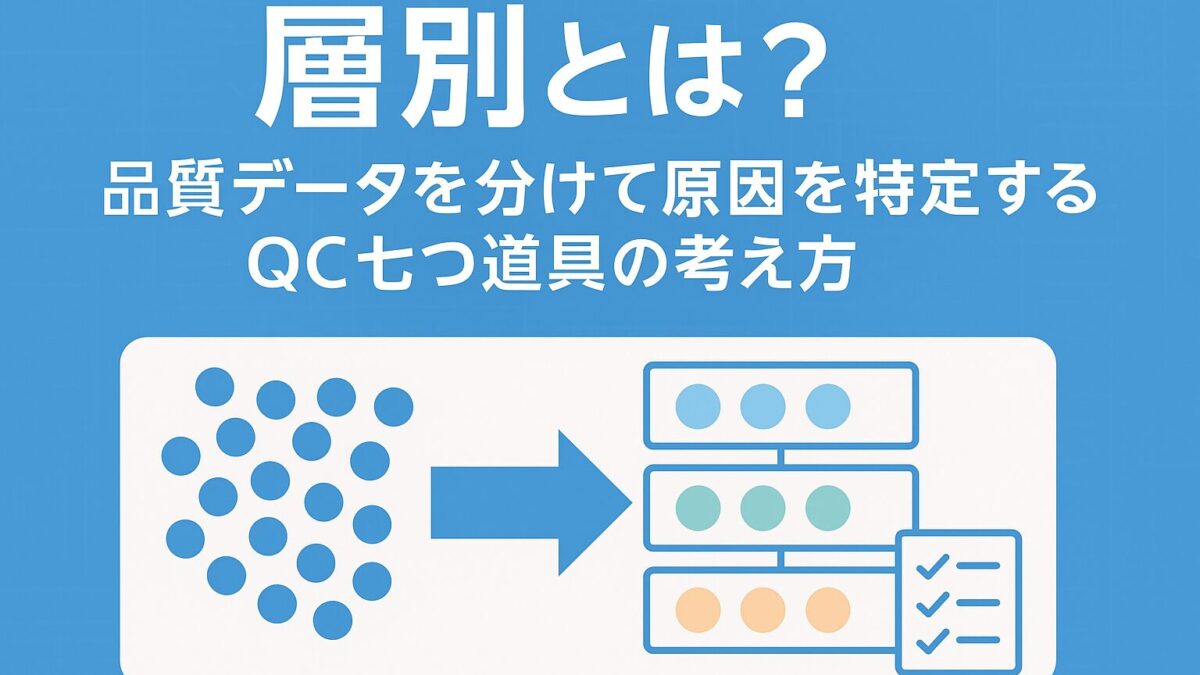品質改善の出発点は、「なぜこの問題が起きているのか」を正しく見極めることです。
そのために欠かせないのが、データを性質ごとに分けて整理する**層別(そうべつ)**という考え方です。
層別とは、収集したデータを人・設備・材料・方法・時間帯などの違いで分類し、傾向を明らかにする手法です。
これにより、全体では見えなかった不良の偏りや工程差が浮かび上がり、
「どの要因で問題が発生しているのか」を明確にできます。
層別はQC七つ道具を使う前の準備段階であり、
適切な層別を行うことで、パレート図やヒストグラムなどの分析結果の信頼性が大きく高まります。
本記事では、層別の基本的な考え方、実践の進め方、そして他のQC七つ道具との関係を、
製造現場出身のコンサルの視点からわかりやすく解説します
QC七つ道具の全体像や各ツールの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ QC七つ道具とは?種類・使い方・事例をわかりやすく解説
層別とは
層別(そうべつ)とは、収集したデータを性質の異なるグループに分け、
傾向や違いを明確にするための分析手法です。
QC七つ道具を使ってデータを分析する前に、まず「どんな条件下で起きているか」を把握するために行います。
層別を行うことで、データをそのまま平均化してしまうことによる誤解を防ぎ、
真の原因を特定するための第一歩となります。
データを分類して傾向をつかむ分析の基本
例えば、「不良率が高い」というデータがあっても、
作業者別、設備別、時間帯別などに分けてみると、
特定の条件下でだけ不良が集中していることが分かる場合があります。
このように層別は、データ全体を細かく分けて見ることで、問題の本質を浮き彫りにする手法です。
平均値だけでは見落としがちな差異を発見でき、改善の方向性をより正確に定めることができます。
QC七つ道具の前に行う“準備のステップ”
層別は、QC七つ道具(パレート図、ヒストグラム、管理図、散布図、チェックシート、特性要因図、グラフ)を使う前段階のステップです。
どのツールを使うにしても、データを適切に分けなければ、
分析結果がぼやけてしまい、誤った判断につながる可能性があります。
つまり層別は、“分析の前提を整える作業”であり、QC活動の精度を左右する要素です。
層別を行う目的と効果
層別の目的は、データのばらつきを「何が原因で生じているのか」を見極めることです。
全体で平均化されたデータではなく、層ごとに整理することで、
異常の傾向・発生要因・再発防止の方向性が明確になります。
また、層別を通じて“問題を特定の現場・条件・人”に絞り込むことができ、
効率的な改善活動の計画立案にもつながります。
層別の切り口(分類軸)
層別を行う際には、まず「どのような観点でデータを分けるか(分類軸)」を決めることが重要です。
分類の仕方によって、見えてくる傾向や原因がまったく異なるため、
現場の状況や目的に応じて最も意味のある層別の切り口を選ぶことがポイントです。
人による違い(作業者・担当者)
作業者や担当者によって品質や作業結果に差が出ることは少なくありません。
経験年数・技能レベル・注意力など、人に関わる要素を切り口に層別することで、
「教育が必要な部分」や「作業標準の理解度の差」などを把握できます。
また、特定の担当者だけに異常が集中している場合は、
標準作業の見直しや指導体制の再構築につなげることができます。
設備や機械による違い
同じ条件で加工していても、設備ごとに精度や安定性が異なることがあります。
そこで、設備番号・ライン別・機種別などでデータを層別すると、
「特定の設備で不良率が高い」「旧型機でバラつきが大きい」といった傾向が浮かび上がります。
設備保全・治具精度・プログラム条件などの違いが原因として特定でき、
予防保全や更新計画の優先順位付けにも役立ちます。
材料やロットによる違い
材料特性や仕入れロットの差が品質に影響する場合も多くあります。
材料メーカー、ロット番号、仕入れ時期などの観点で層別することで、
「特定ロットで不良が多い」「仕入先Aの方が安定している」などの傾向を把握できます。
これは特に、化学品・金属・樹脂など材料品質のばらつきが影響しやすい業種で重要です。
時間帯・作業条件による違い
作業時間帯や環境条件によっても品質が変動することがあります。
昼夜交代制の職場では「夜勤の方が不良が多い」、
温度や湿度が影響する工程では「夏場に寸法不良が増える」といったケースが見られます。
時間帯・気温・湿度・稼働日数などで層別することで、
環境条件や作業負荷の影響を定量的に把握することができます。
層別の進め方
層別は、やみくもにデータを分けるのではなく、目的を持って整理・分析することが重要です。
ここでは、現場で実践しやすい3つのステップで層別の進め方を解説します。
① 分析目的を明確にする
最初に、「何を明らかにしたいのか」を明確にします。
たとえば、
- 不良の原因を特定したいのか
- 工程間のばらつきを把握したいのか
- 作業条件と品質の関係を調べたいのか
目的によって、どの切り口で層別するかが決まります。
目的が曖昧なまま層別すると、無意味にデータを細分化してしまい、
かえって傾向を見失う原因になります。
「分析目的 → 分類軸の設定 → データ収集」 の順で進めるのが基本です。
② データを適切に分類・整理する
次に、設定した分類軸に沿ってデータを分けて整理します。
このとき、層を細かくしすぎるとデータ数が少なくなり、信頼性が下がるため注意が必要です。
また、複数の層別を同時に行う(例:人×設備、材料×時間帯など)場合は、
交互作用(複数要因の組み合わせで生じる影響) にも着目しましょう。
表やチェックシートでまとめておくと、後の分析がスムーズに進みます。
(→ チェックシートとは?品質管理の現場で役立つQC7つ道具をわかりやすく解説)
③ 分類結果を見える化して傾向を確認する
層別したデータを表やグラフで可視化し、傾向を確認します。
棒グラフやパレート図を使えば、層ごとの違いを一目で把握できます。
(→ 現場改善最初の一歩!誰でも簡単PQ分析!パレート図でなんでも見える化!)
また、ヒストグラムで分布の広がりを確認したり、散布図で関係性を探るなど、
他のQC七つ道具と組み合わせることで、より正確な分析が可能になります。
層別の目的は「原因の見える化」。グラフ化を通して、どの層で偏りが起きているかを明確にすることが重要です。
層別したデータを視覚的に表す際には、
→ グラフとは?品質データの見える化で改善を促すQC7つ道具を解説
→ 現場改善最初の一歩!誰でも簡単PQ分析!パレート図でなんでも見える化!
→ ヒストグラムとは|品質のばらつきを見える化するQC7つ道具の基本
などのツールを組み合わせると効果的です。
層別の活用例
層別は、データ分析の基礎であると同時に、改善テーマを明確化する実践的な手法でもあります。
ここでは、製造現場で実際に成果を上げやすい3つの活用例を紹介します。
不良の発生傾向を特定する
不良データを層別することで、どの条件下で不良が多発しているかが明確になります。
例えば、不良の発生件数を「設備別」や「作業者別」で分けると、
全体では平均的に見えるデータの中に、特定条件での偏りが現れることがあります。
その傾向をパレート図に展開すれば、重点的に対策すべき領域を特定できます。
(→ 現場改善最初の一歩!誰でも簡単PQ分析!パレート図でなんでも見える化!)
工程ごとのばらつきを把握する
工程ごとの品質特性値(例:寸法、重量、粘度など)を層別することで、
「どの工程でばらつきが大きいか」「どの条件で安定しているか」を定量的に把握できます。
この情報をヒストグラムや管理図に展開すれば、工程能力の見える化や異常の早期発見につながります。
(→ ヒストグラムとは|品質のばらつきを見える化するQC7つ道具の基本)
(→ 管理図とは?品質改善につながるQC7つ道具 見方や使い方を解説)
重点改善テーマを決める
層別を行うと、データの中から「どこに問題が集中しているか」が明確になります。
これを基に、改善の優先順位を決めることで、効果的な活動が可能です。
例えば、「材料ロットごとに不良率を層別 → 特定ロットでの不良多発を確認 → 原因を特性要因図で深掘り」
といったように、層別は問題発見から原因分析への橋渡しの役割を果たします。
(→ 特性要因図(フィッシュボーン図)とは?意味・書き方・例を徹底解説)
まとめ
層別は、データを正しく理解し、問題の本質を見抜くための第一ステップです。
全体の平均値だけを見ていては、重要な傾向や偏りを見逃してしまいます。
「誰が」「どの設備で」「どの条件で」問題が発生しているのかを明確にすることで、
改善の方向性がはっきりと見えてきます。
層別は、QC七つ道具の中でも“前提となる分析”として位置づけられます。
適切にデータを分類することで、パレート図・ヒストグラム・散布図などの分析精度が高まり、
正しい判断と効果的な対策につながります。
品質改善の成果は、データの見方で大きく変わります。
層別を通じて「全体ではなく、層ごとに見る」という習慣を身につけることが、
現場の改善力を根本から高める第一歩です。