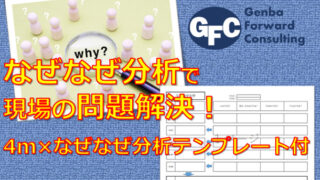現場でトラブルや不具合が発生したとき、「原因は○○だった」と表面的な結論にとどまり、再び同じ問題が起きてしまう──そんな経験はありませんか?
この繰り返しを断ち切るために有効なのが なぜなぜ分析(5 Whys) です。
シンプルに「なぜ?」を繰り返すだけの手法に見えますが、実際にやってみると 問いが浅くなる・議論が迷走する・真因にたどり着けない など、思った以上に難しいものです。
そこで本記事では、製造現場出身コンサルが、現場改善で実際に使われている手順とコツを整理し、なぜなぜ分析を正しく進める方法を紹介します。
初めて実践する方はもちろん、これまでうまく使いこなせなかった方にも役立つ内容です。
なぜなぜ分析とは?
基本の考え方(5 Whys)
なぜなぜ分析は、トヨタ生産方式から生まれたシンプルかつ強力な問題解決手法です。「なぜ?」と問いを繰り返し、表面的な原因ではなく根本原因(真因)を突き止めることを目的とします。一般的に5回程度繰り返すため「5 Whys」と呼ばれています。
重要なのは、「逆から読んでも因果関係が成り立つ」ことです。つまり、最後に整えた仕組みがあれば、その上流の問題が自然に消えていく構造になっていること。これが、なぜなぜ分析を成功させる大前提です。
現場で使われる理由(再発防止・真因特定に有効)
現場では「作業者の不注意」といった表面的な結論で片付けられるケースが多くあります。
しかし、それでは再発を防げません。
なぜなぜ分析を活用すると、「教育不足」「治具の寿命管理がない」「確認工程の設計不足」といった仕組みの欠陥が浮かび上がります。
ここで大切なのは、ルール強化ではなく仕組みづくりに結びつけることです。
ルールは「守ろうとしないと守れない」ものですが、仕組みは駐車場の白線のように「自然に従ってしまう」ものです。
現場に定着するのは仕組みであり、これがなぜなぜ分析の本当の強みです。
なぜなぜ分析の進め方(5ステップ)
① 問題を明確に定義する
「いつ・どこで・何が起きたか」を事実ベースで整理します。
曖昧なまま始めると途中でぶれます。具体的な現象を共通認識として持つことが出発点です。
② 「なぜ?」を繰り返して原因を深掘りする
最初の答えは多くの場合「表面的な原因」です。
さらに「なぜ?」を重ねることで、仕組みの欠陥や環境要因が見えてきます。
責任追及ではなく仕組み改善を意識します。
③ 真因を特定する
複数の原因が出てきても、「ここを直せば上流の問題が自然に消える」ものが真因です。
逆から読んでもつながる因果関係を意識して整理することが大切です。
④ 対策を立案する
真因に対応する対策を考えます。
「注意喚起」ではなく「仕組みの変更」に結びつけることが再発防止の条件です。
⑤ 再発防止の仕組みに落とし込む
改善策を現場の仕組みに組み込みます。
作業標準書の改訂、チェックリスト、ポカヨケ、アラート設定など、自然に従わざるを得ない形にすることがゴールです。
現場でよくある失敗と回避のコツ
- 「なぜ?」が浅く止まる → 「不注意」で終わらせず、さらに掘り下げる
- 原因が多すぎて収束しない → 因果関係を整理し「逆から読んでも筋が通る」かで確認する
- 形だけで終わる → 改善策を「ルール強化」ではなく「自然に従ってしまう仕組み」に落とし込む
なぜなぜ分析の活用事例(仕組み視点)
不良品(製品にキズがついた)
- なぜ? → 加工中に治具と部品がぶつかった
- なぜ? → 治具が摩耗して正しい位置を保てなかった
- なぜ? → 治具交換が行われていなかった
- なぜ? → 点検・交換の仕組みがなかった
- なぜ? → 治具寿命を管理する仕組みを最初から設けていなかった
真因:治具寿命を管理する仕組みの欠如
対策:交換時期を自動で知らせるカウンターを設置し、自然に交換される仕組みを導入
納期(出荷が遅れた)
- なぜ? → 組立の開始が遅れた
- なぜ? → 必要な部品がそろっていなかった
- なぜ? → 部品発注が遅れた
- なぜ? → 発注期限を事前に把握できていなかった
- なぜ? → 発注期限を自動で見える化する仕組みがなかった
真因:発注期限を管理する仕組みの欠如
対策:生産管理表に「発注期限アラート」を組み込み、自然に期限を守れる仕組みにする
ヒューマンエラー(誤った部品を組み付けた)
- なぜ? → 作業者が似た部品を取り違えた
- なぜ? → 部品置き場が隣同士で区別しづらかった
- なぜ? → ラベルや色分けがされていなかった
- なぜ? → 部品識別の仕組みが整っていなかった
- なぜ? → 誰でも分かる識別方法を最初から設けていなかった
真因:部品を識別する仕組みの欠如
対策:部品置き場を色で区分し、大きなラベルを貼る。誰でも間違えない仕組みにする
まとめと次のステップ
なぜなぜ分析は「人の不注意」を責めるのではなく、「自然に従ってしまう仕組み」をつくるための思考法です。
特に意識すべきは次の2点です。
- 逆から読んでも因果が通る筋道をつくること
- ルールではなく仕組みで再発防止を図ること
この視点を持つことで、なぜなぜ分析は単なる原因追及ではなく、現場に改善文化を根付かせる武器となります。まずは身近なトラブルから始めて、小さな仕組み改善を積み重ねてみましょう。
フォーマットについては、こちらの解説記事をご覧ください。
【無料フォーマット付】なぜなぜ分析(5Whys)の実践法